『梅雨が来る前に♪ クロッタを、何とか早く、仕上げてしまいたい~♪』
と日々頑張りました。
1時間片づけは1月以上続いていましたが、
背に腹は替えられず、あっけなく終わってしまいました。
あれだけ好調だったのですが…
しかし、それでも、やはり、思ったようには物事は進んでくれませんでした。
それどころか、
梅雨が明けてしまいました!
あっけなく!
今年の梅雨明けはなんて早いのでしょう。
それでも、何とか塗装もあと少しで終わりです。
磨いては塗り、磨いては塗りの繰り返しで大変ですが、
美しく仕上がっていくのが楽しみです。

ふと気が付くと、
毎年梅雨前に同じ歌を歌っている気がします。
全く成長できていない自分に気が付きます。
言い訳としては、
毎年、4月にドイツから戻ってから作り始めるため、
どうしても期間が足りなくなってしまうのです。
また、ありがたいことに、
他にたくさんの仕事をいただくために、
どうしても延び延びになってしまいます。
あっ、それと、
今回はドイツに行く前にザーレムライア第一号も作り上げました。
それも要因の一つです。
まあ、実際の作業は思った以上に時間がかかるということです。
「こんな感じでこうやって進められるだろう。」
と机上の空論で時間を見積もっても、
だいたいその2倍から3倍は軽くかかってしまいます。
私の想像力の欠如でしょうか?

よりきれいに、早く仕上げられたらと思い、
新しい道具を使って作業することがあります。
でも、やったことがないことは想定外の事が起こり大変です。
今回は、それが災いして一台台無しにしてしまいました。
とほほ……
実際にやってみて、初めて気が付くことが結構たくさんあります。
トーンチャイムなるものを作り始めた時のことです。
トーンチャイムとはアルミ管を吊るして打棒でたたいて音を出す楽器です。
432Hz や528Hzなどのソルフェージョ音階に正確に調音していきます。
「管を短くしていけば、音が上がっていくんだよね♪」
と思いながら管を少しずつ削っていきます。
削っては音の高さを測って確かめます。
とても手間のかかる作業ですが、ゴールは見えています。
ところが、実際に作業してみると、
音の高さが上がったり下がったりと、
毎回微妙に違った結果が出て頭が混乱します。
そして、管の叩く場所を変えることで、
音の高さが変わってくることに初めて気が付きます。
「こんなこと、どこにも書いてないよ~!」
「ウィキペディアにも!」
お手上げです。

それまで単純なことだと高をくくっていたものが、
実際はとても複雑なものだということに身をもって気づかされます。
実際にやってみることで、同じような体験をすることが多々あります。
実際に作業することで、今まで知らなかった側面に気づき、
そのものに対して より深く理解できるようになっていきます。
そして、そのものに対して尊敬のまなざしが生まれ、
自分が謙虚になっていくような気がします。
ありがたいことです。
自信も失われていきますが…
きっと、自分の身の回りにある簡単に見える物の中にも、
たくさんのことが込められているのでしょう。
人や団体との出会いも同じような気がします。
実際にその場に行ったり、その人に会ったりすることで、
それまで 思い描いていたイメージとは全く違うものがそこに生まれてきます。
その中にある奥深い世界を感じ、尊敬の念が生まれてきます。

* *
日々、学びを深めながら、目の前の課題をがむしゃらにこなしながら、
ふと気づけば70歳間近です。
そろそろ自分の人生を振り返ってみる時期なのかもしれません。
いや、とうにふり返っておくべきだったかもしれません。
いやいや、その前に、たまりたまった未整理の物の山を片付けなければなりません。
これまで、なんとか暮らせてきたのも、周りの支えのおかげです。
感謝です。
ありがとうございます。
いろんなことが便利になり、作業も早くできるようになっているはずなのに、
より忙しく、時間がなくなってきているのは気のせいでしょうか。
長い間続けてきた教室も 一つまた一つとたたんで行っています。
私が教室を始めた35年ほど前は、まだシュタイナー学校はありませんでしたが、
今では 各地でたくさんの学校や教室が開かれています。
私の役目も終わったのだと思います。
何らかのきっかけになってくれたとしたら嬉しいことです。

教室を続けてきたことでたくさんの子ども達との出会いがありました。
そんな中で、大きくなって連絡をくれたり、ペロルに訪ねて来てくる子がいます。
とても嬉しいことです。
会って、話をして、その立派になった姿に目をみはるばかりです。
そしてR・シュタイナーの言葉を思い出します。
<子どもたちに向かう時は幼い存在として対応するのではなく、
自分よりもはるかに立派な大人になる存在と向き合っていることを意識すべきだ>
という言葉です。
まさにその言葉の通りです。
「私は目の前の立派になった子たちにその当時向かっていたのだ!」
ということを思い起こさせます。
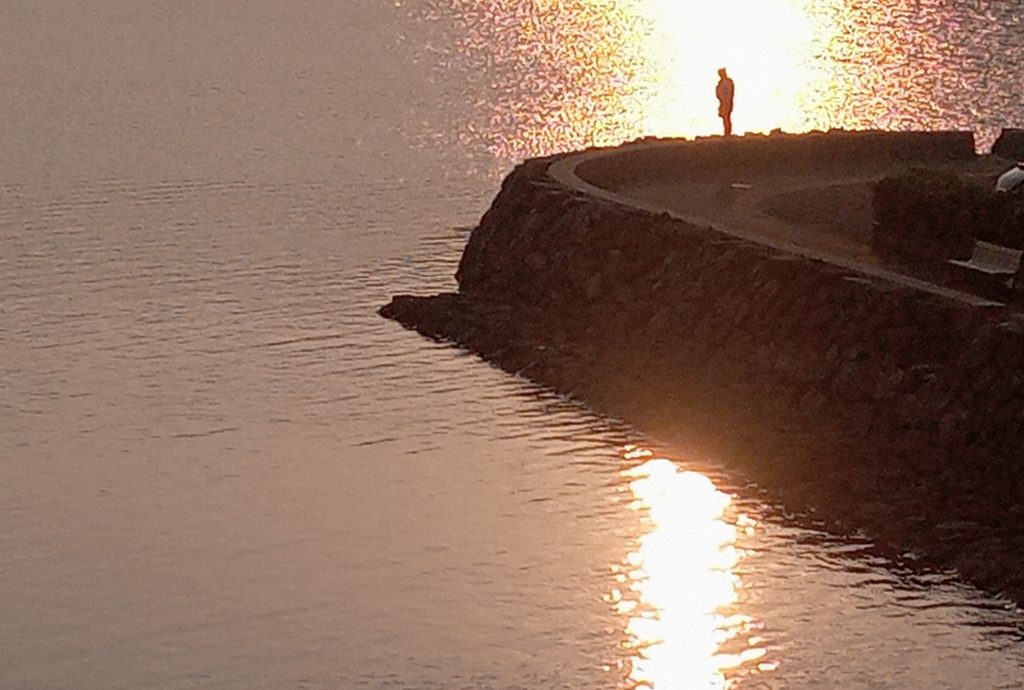
他の言葉も思い出されます。
「子どもの時はわからないけれど、
理解できる年代になった時に、
初めてそのことが一体どういうことだったのかを理解する。」
という言葉です。
自分自身にも経験があります。
小学校6年生の時の話です。
とても立派な担任の先生が、ある時 やんちゃな男の子にかけた言葉が思い出されます。
ある出来事が起き、そのやんちゃな男の子のせいにされました。
後でその子のせいではないことが分かった時、
先生は
「おまえが、いつもわるいことをするから疑われるのだ。」
と言ったのです。
私は、その時何とも言えない違和感を覚えたのですが、
なんなのかは分かりませんでした。
歳月が経って、
あの言葉は先生の失言だった、ということに気が付きました。

私自身も気が付かないうちにたくさんの失言をしていることでしょう。
時々、自分の子どもに、
「自分が小さいときにパパはこんなことを言ったり、やったりした。」
と言われることがあります。
やはりそのようです。
子どもが大きくなってそのことを言えるだけ、まだましかな、
と自分を慰めています。
2025/07/04 井手芳弘
